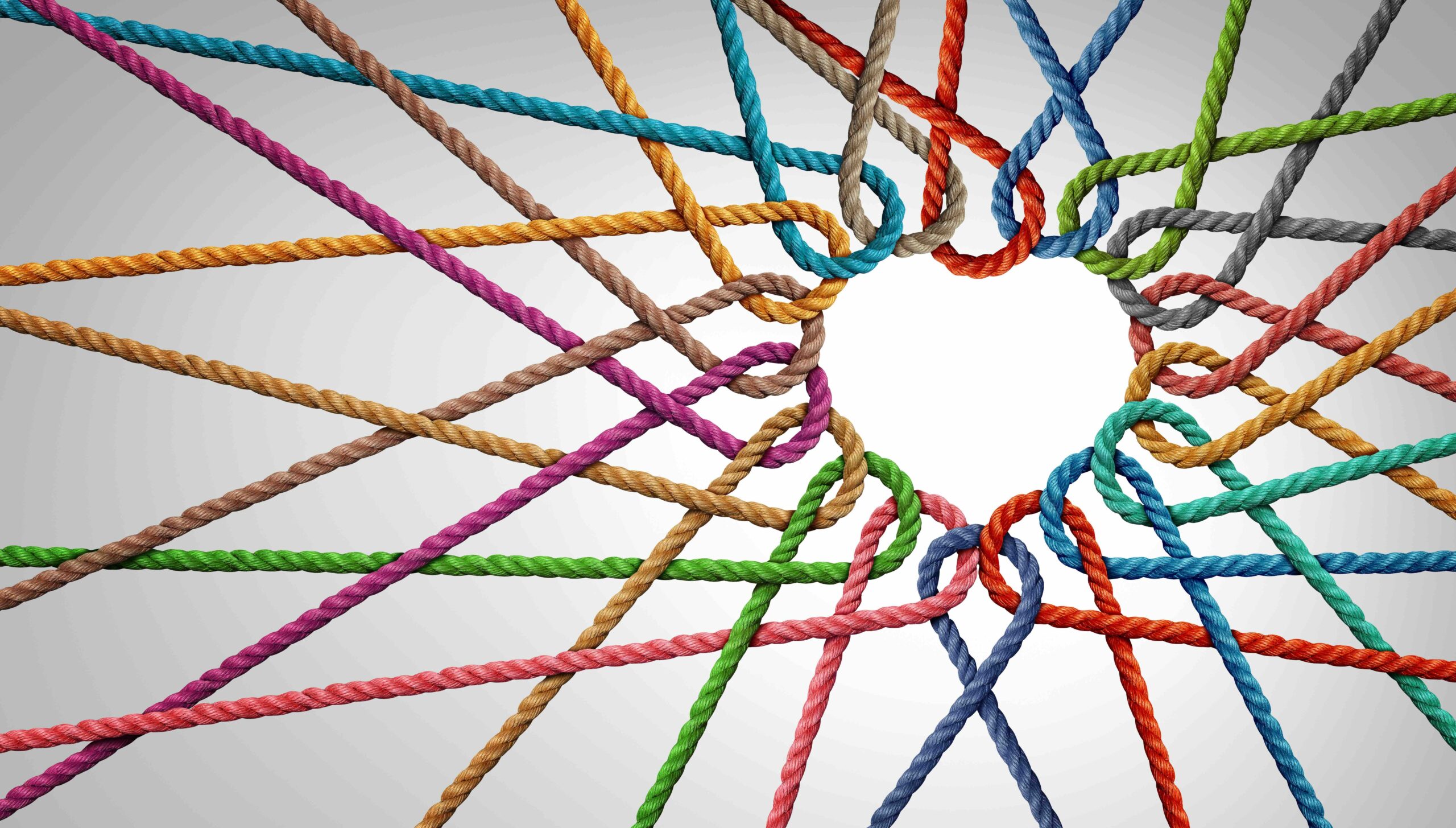
嘘くさい家族【ブッダスクール通信vol.67】
みなさま、こんにちは!
ブッダスクール通信メルマガ担当のさめじまみおです。
桜、満喫されましたか?
東京は見ごろを過ぎてしまったのですが、少し
寒い地方の方とお話ししていたら、
「こちらはこれからなんです!週末が満開かな」
と弾んだ様子だったので、うらやましく思いました。
桜前線を追いかけていきたくなるお年頃。
子どものころは「桜?ふーん」という感じだった
のに、歳を重ねるごとに、お花が愛おしくなりますね。
さてさて、そんなお花ラブの気持ちとともに、
ちょうど桜と菜の花の咲く千葉県は富津市へと
先月、旅行に行ってきたのです。
だれと?家族と?ひとりで?
いえいえ、なんと30年ぶりに顔を合わせる
高校時代の親友ふたりとの、女三人の旅でした。
そのことをブログなどに書いたところ、
数名の方からの感想で、ちょっと意外なポイントが
書かれていたのでした。
……の、つづきは編集後記にて。
さてさて、お待たせしました!
ここでしか読めない
つうりさん特別コラムにさっそくいってみましょう。
■━━━━━━━━━━━■
〔1〕齊藤つうり特別コラム
「嘘くさい家族」
■━━━━━━━━━━━■
子供たちの春休みにあわせて、ウチの寺に
友人・家族たちが集まった。
私たちを含めて、総勢で10名ほどの大人と子供が、
三日間ほど過ごした。
独り身の人もいれば、シングルマザーの人もいて、
さらには離婚した元夫と、再婚相手の子供までいた。
なので、いわゆる「夫婦と子供からなる家族」が
集まったわけではく、カオス溢れる集いとなった。
ちょうど見頃の桜の下、皆でお茶を飲み、
食事の席を囲んだ。
大人たちはそれぞれ話をし、子供たちは
そこらじゅうを走り回ったり、隠れたりしていた。
どこにいっても人がいて、皆がそれぞれに楽しんでいた。
特に目的もなく、ただ皆でわいわいと時間を過ごした。
私はこの拡張家族が好きだ。
私にとって、この拡張家族という言葉は、夫婦や
誰の子供という枠組みを超えて、関係性がはっきり
しない人たち同士が一堂に集って、大きな家族の
ようなものを作っている状態を指す。
私が生まれた寺には、いつでも大勢の人がいた。
私の父母も、そして祖父母も人を招くのが好きだった
こともあり、食事の時にはいつも10名以上の人が
いたように思う。
皆、わいわいと酒を飲み、タバコを山のように
吸って、いつまでも座敷に集まっていた。
そこで育った私にとって、どこからどこまでが
自分の家族という感覚が薄かった。
だからなのか、こうして世代やら性別やらが
ごっちゃになり、わいわいと暮らしている様子が、
私にはなぜか心地良い。
メルマガだから好きに書いてしまうんだけど、
逆に私にとっては、両親がいて、そこに子供が
いて、完結しているという構図に、少し居心地の
悪さを感じる。
もっと言えば、嘘くさく感じてしまう。
なんというか「ほんとうはそこだけで完結できる
はずがないのに、無理に完結させてしまっている」
という感じがする。
もしも私が父母と兄弟だけの環境のなかで育った
としたら、私にとって、とても窮屈に感じたと思う。
まるで大きく育った観葉植物の鉢を取り替えるとき、
根がぎゅうぎゅうにつまっているみたいに。
この日本という国はおそらく、この拡張家族の
形態がずっと続いてきた場所だ。
皆が住まう大きな家があって、ゆるい境界線の
なかで暮らす。
そこには仕事をしている人はしているし、
していない人もいる(江戸時代には十人に一人が
引きこもり、あるいは働いていない人だったという
データがある)。
血が繋がっている人もいれば、そうでない人もいる。
近代に入る以前は、そんな暮らしがずっと続いていたはずだ。
そして特定の個人が、誰かを養う・養われるという
感覚ではなく、皆で養い合っているという感覚が
そこにはあったはずだ。
そしてまたいま現在の家族という形態―夫婦、
あるいはそこに子供がいる―は、解体され、今後
また拡張家族に必ず戻っていくと私は予想する。
ついこの間まで主流だったように見えたこの夫婦関係、
あるいは核家族の形態は、日本が経済発展を遂げる
ために一時的につくられたもののように私には思える。
現代の家族と呼ばれる形態はあまりにも窮屈で
あるために、いまの若い人たちはそのような家族を、
自分も持ちたいとは考えない人が多いのではないだろうか。
また今の時点で結婚を選択していない人たちも
なんというか「いまの家族の一時的で、持続性がない、
不完全なもの」に自分のすべてが絡められていく
ことの煩わしさ、嘘くささのため「家族を持つ」と
いう選択をしない人が多いのではないだろうか。
そんな人たちにぜひ勧めたいのは「拡張家族」を
やってみることだ。
二、三家族、あるいは複数名で集まり、ただ話して、
飲んで、食べて2、3日過ごす。
そこには何の目的や利益を持ち込まない方がいい。
大切なのは、ある程度信頼がある人たちで集い、
寝食を共にすること。
そうするとそこには「不思議と満たされた感覚」が
あるはずだ。
そして普段、何をやっても満たされない感じや
不足感が、拡張家族でいる時には、消えていることに
ふと気がつくだろう。
こんなふうに書くと、「私はそもそも人がいる
状態ではリラックスできないから」という人も
いると思う。
実は私もそういうタイプだ。
一人で過ごす時間が何より大切だし、一番
リラックスする時は間違いなく一人の時間だ。
けれどここで伝えたいことはそれとは少し違う。
「家族」とはそもそも何か、ということを
私はここで言いたいのだ。
そしてまた私たちが今持っている「家族」という
感覚は、擬似的につくられたものであって、
本来はもう少し大きなものであったはずではないか、
ということを言いたいのだ。
人間という存在は、心の内側にあるものと、
外側にあるものを重ねながら、気づきを得ていく存在だ。
そうだとするならば、すぐ目の前にいる家族たちが
限られた人数であれば、それだけの気づきしか
得ることができないとも言える。
逆に家族が多ければ多いほど、より多くの
気づきと自己を体験できる可能性が生まれると言える。
ひょっとしたら、現代の私たちが陥りやすい
「家族を守らねば」という病も、「どうせ誰とも
分かり合えないのなら自分一人でいいや」という
思いも、「誰かが作った偽の家族の枠組み」から
生まれたものなのかもしれない。
そしてその「嘘くさい家族」の枠組みにしっかり
直面したときに、本当の意味での家族を持ちたいと
願えるようになるのかもしれない。
寺の庭に雪みたいに降る桜の花びらと、
大人たちの話し声と、子供たちの笑い声。
懐かしい未来はここにあるのかもしれない。
■━━━━━━━━━━━■
〔2〕最新スクール情報
■━━━━━━━━━━━■
【募集中】Total Integration Course ー自己統合と魂のビジョンー
2025年5月10日(土)開講 《全講義オンライン形式》
Total Integration Course は、自己統合と個性化の
ビジョンのための新しいプログラム。
スクールの根幹である自己統合クラスと弥勒力
クラスをひとつの流れとして昇華させることで、
「個性化のスクール」としての本質をより
磨き上げた形へとステップアップしました。
本コースは、過去と未来を統合し、本質的な
生命力を得て、なれる最高の自分(=個性化)を
生きるための9ヶ月のプログラムです。個性化とは、
あなた自身が本来持つ個性に触れることで、本来
そうなるであろうあなた自身へと統合されていく
プロセスのこと。最終的には「個性化の道ーなれる
最高の自分ー」へとつながる道を参加者は見出すことで、
高度かつ柔軟なスピリチュアリティを獲得し、認識の
空を羽ばたく、大きな自由を獲得することでしょう。
世界がその古い殻を脱ぎ捨て、新しいありようへと
変容するその瞬間、あなた自身もまた新しい自己へと
ひらかれるタイミングを迎えているはず。
この2025年の「地球が覚醒する一年」により、あなた
自身が開かれ、外の世界と結びつくその瞬間こそ
「目覚め」を体験するタイミングといえるでしょう。
■━━━━━━━━━━━■
〔3〕編集後記
■━━━━━━━━━━━■
ふだんは特にもらうことも少ないブログのご感想。
それが、今回はぱたぱたと届きました。
おどろきましたが、そこに書かれていたことに
わたしはもっとおどろいたのです。
そこに書かれていたのは、
「家族以外の人と旅行に行けるなんてすごい。
私にはムリ」
「うらやましいけど、緊張して疲れちゃいそう」
というもの。それが何人もの方から届いたのでした。
その反応に、ハッとしました。
わたし自身もきっと、以前のわたしだったら、
そう言っていたかもしれない。でも今回は、なんの
遠慮もなく旅を楽しんでいる自分がいました。
旅先では、いつもよりずっと長い時間を誰かと
一緒に過ごします。朝起きてから夜眠るまで。
食べる、歩く、話す、黙る――
そんな「生きる時間のすべて」が交差する。
でも、そこで感じたのは「しんどさ」ではなく、
不思議な自由でした。
たとえば、わたしがひとりで部屋にこもっていても、
ふたりはなにも言わないし、そっとしておいてくれる。
逆に、わたしと友人が盛り上がっているとき、
他のひとりが静かに窓の外を見ていても、それでOKだった。
そこには、「合わせなきゃ」「仲良くしなきゃ」という
無意識の努力が必要なかったんです。
それぞれが自分のペースを大事にしているから、
相手のペースにも自然に敬意が生まれる。
もしかすると、それが「寝食を共にできる」
ということの本質なのかもしれません。
家族だから、親子だから、親友だから、あるいは
ひとりだから、自由で自分らしくいられる。
のではなく、
寝食をともにしながら、同じ空間で同じ景色を
眺めながら、肌感覚としかいいようのないものを
そっと触れ合わせながら、
わたしたちは、自分のままで、
それ以上に、自分というものをふっと手放しながら
誰かとともにいることができるのかもしれない。
わりといつでも排他的なところのある、個人主義の
わたしの中のなにかが、少しだけゆらいだ春の旅でした。
今日も最後までお読みくださり、ありがとうございました!
文責:さめじまみお












この記事へのコメントはありません。